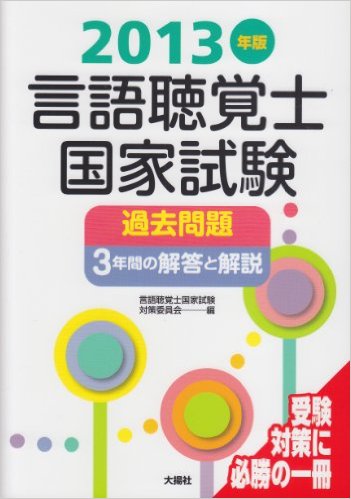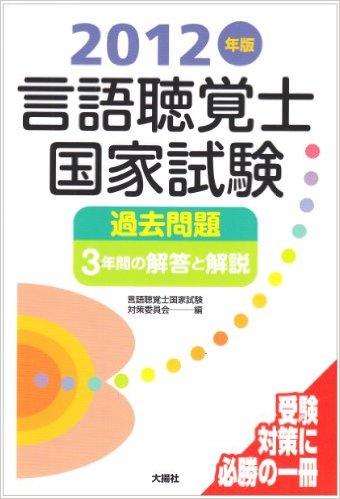第1問 職種と業務との組み合わせで正しいのはどれか。
1. 医師 - リハビリテーション処方
2. 理学療法士 - 聴力検査
3. 作業療法士 - 義足作成
4. 言語聴覚士 - 気管カニューレ交換
5. 看護師 - 嚥下内視鏡検査
第2問 母子保健法について誤っているのはどれか。
1. 乳児とは2歳に満たない児と規定されている。
2. 新生児とは出生後28日間を経過していない児と規定されている。
3. 母子健康手帳は自治体から交付される。
4. 3歳児健康診査は母子保健法に規定されている。
5. 出生体重2500g未満の場合、自治体に届け出なければならない。
第3問 口唇の知覚に関わる神経はどれか。
1. 迷走神経
2. 副神経
3. 顔面神経
4. 三叉神経
5. 舌下神経
第4問 視覚路に含まれないのはどれか。
1. 視索
2. 視放線
3. 視床前核
4. 視交叉
5. 外側膝状体
第5問 誤っている組み合せはどれか。
1. アルツハイマー病 - 認知症
2. 脊髄小脳変性症 - 失調
3. デュシェンヌ型筋ジストロフィー - 近位筋萎縮
4. ギラン・バレー症候群 - 呼吸障害
5. 筋萎縮性側索硬化症 - 同名性半盲
第6問 誤っている組み合せはどれか。
1. アルブミン - 栄養
2. ALT(GPT) - 肝機能
3. クレアチニン - 腎機能
4. クレアチンキナーゼ - 糖尿病
5. 尿酸 - 通風
第7問 誤っているのはどれか。
1. 胃癌は男性に多い。
2. 潰瘍性大腸炎は原因不明の炎症性腸疾患である。
3. 胃ポリープは大腸ポリープと比べて癌化する率が高い。
4. 胃潰瘍の発症にヘリコバクター・ピロリ菌の感染が関与している。
5. 我が国において大腸癌は増えている。
第8問 誤っているのはどれか。
1. うつぶせ寝は乳児突然死症候群の危険因子である。
2. 1歳児の最も多い死因は不慮の事故である。
3. ピーナッツは気道異物の原因となる。
4. 1歳児の溺水の事故は河川で起こることが多い。
5. 蜂蜜は乳児には禁忌である。
第9問 正しい組み合せはどれか。
1. ウィリアムス症候群 - 自閉傾向
2. 歌舞伎症候群 - 高身長
3. ターナー症候群 - 高身長
4. ソトス症候群 - 低身長
5. CHARGE症候群 - 難聴
第10問 自己や外界に対して生き生きとした現実感が感じられなくなることで定義される症状はどれか。
1. 離人症
2. 妄想気分
3. 思考奪取
4. 白昼夢
5. 昏迷
第11問 誤っている組み合わせはどれか。
1. 構音障害 - 文字盤使用
2. 顔面神経麻痺 - マッサージ指導
3. 嚥下障害 - 嚥下造影検査
4. 記憶障害 - メモリーノート使用
5. 運動性失語 - 人工喉頭
第12問 写真に示すのはどれか。
1. 足底板
2. 長下肢装具
3. 短下肢装具
4. 大腿義足
5. 下腿義足
第13問 ハント症候群でみられる症状はどれか。
a.めまい
b.単純疱疹
c.伝音難聴
d.耳下腺腫脹
e.顔面神経麻痺
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第14問 口腔乾燥症の原因でないのはどれか。
1. 脱水症
2. 唾石症
3. 放射線照射
4. 薬物の副作用
5. シェーグレン症候群
第15問 55歳の男性。右利き。最近1週間に3回、約20分続く右の片麻痺と左眼の暗黒感が出現するため来院した。障害動脈はどれか。
1. 右中大脳動脈
2. 右内頸動脈
3. 椎骨脳底動脈
4. 左内頸動脈
5. 左中大脳動脈
第16問 基底細胞が構成するのはどれか。
1. 表皮
2. 真皮
3. 毛髪
4. コラーゲン
5. 毛細血管
第17問 歯周病について正しいのはどれか。
1. 歯槽骨骨髄の脂肪化
2. 口腔カンジダ菌の増殖
3. 口腔粘膜の上皮異形成
4. 歯髄の変性壊死
5. 歯の病的移動
第18問 味覚に関与しない脳神経はどれか。
a.三叉神経
b.顔面神経
c.舌咽神経
d.迷走神経
e.舌下神経
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第19問 正しいのはどれか。
1. 肺側胸膜は肺の表面を覆う。
2. 壁側胸膜は胸郭の外面を覆う。
3. 肺の実質と肺側胸膜の間を胸膜腔という。
4. 肋骨は13対ある。
5. 肋間筋を支配する胸神経は12対ある。
第20問 顔面神経支配でないのはどれか。
1. 前頭筋
2. 側頭筋
3. 眼輪筋
4. 口輪筋
5. 広頸筋
第21問 正しいのはどれか。
1. 音の大きさの感覚は音の周波数と関係しない。
2. 中耳伝音系によって音エネルギーが付加される。
3. 音の左右時間差に関与する最下位の中枢は上オリーブ核である。
4. 内耳性難聴の特徴として一過性閾値上昇がある。
5. 内耳有毛細胞の働きが基底板の鋭い周波数特性をもたらしている。
第22問 難聴の変動や進行がないのはどれか。
1. メニエール病
2. 先天性サイトメガロウイルス感染症
3. 聴神経腫瘍
4. 前庭水管拡大症
5. 耳小骨連鎖離断
第23問 網掛け部分がブローカ野を含む図はどれか。
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E
第24問 アルツハイマー病の初期にみられるMRI所見はどれか。
1. 小脳の萎縮
2. 脳幹の萎縮
3. 海馬の萎縮
4. 前頭葉の浮腫
5. 大脳白質の異常信号
第25問 ゲシュタルト要因でないのはどれか。
1. 近接
2. 類同
3. 閉合
4. よい連続
5. 親近
第26問 負の強化はどれか。
1. 行動の結果好ましくない事態が取り除かれることにより、その行動の頻度が増大する。
2. 行動の結果好ましくない事態が生じることにより、その行動の頻度が減少する。
3. 行動の結果好ましい事態が取り除かれることにより、その行動の頻度が増大する。
4. 行動の結果好ましい事態が生じることにより、その行動の頻度が増大する。
5. 行動の結果好ましい事態が取り除かれることにより、その行動の頻度が減少する。
第27問 経験則に基づいた直観的な問題解決法はどれか。
1. ヒューリスティックス
2. アルゴリズム
3. フラッディング
4. フォーカシング
5. サッケード
第28問 信頼性と関係ないのはどれか。
1. 再検査
2. α係数
3. 上下法
4. 項目得点相関
5. 上位-下位分析
第29問 正しいのはどれか。
1. 名義尺度上の測定値は差をとることができる。
2. 順序尺度上の測定値は大小関係を保存する単調変換を施すことができる。
3. 5段階評定による測定値は比率尺度である。
4. 順序尺度上の測定値は分散を求めることができる。
5. 比率尺度上の側低値は原点を任意に変換することができる。
第30問 防衛機制として適切でないのはどれか。
1. 投影
2. 抑制
3. 合理化
4. 昇華
5. 退行
第31問 神経性無食欲症について正しいのはどれか。
1. 不安障害の一つである。
2. 女性より男性に多い。
3. 薬物療法は無効である。
4. 家族関係は良好に保たれる。
5. 自尊感情が低く、うつ状態を伴う。
第32問 WISC-Ⅳ知能検査の下位検査でないのはどれか。
1. 知識
2. 符号
3. 数唱
4. 迷路
5. 理解
第33問 Vygotsky,L.S.に関係するのはどれか。
1. 外言・内言
2. 双生児統制法
3. 発達段階論
4. 成熟優位説
5. 視覚的断崖実験
第34問 正しい組み合せはどれか。
1. 量の保存 - 三つ山問題
2. 友人関係 - ストレンジ・シチュエーション法
3. 児童の愛着 - 誤信念課題
4. 乳児の知覚 - 選好注視法
5. 象徴機能 - 馴化・脱馴化法
第35問 青年期に関係ないのはどれか。
a.形式的操作段階
b.自律性の獲得
c.ギャングエイジ
d.モラトリアム
e.性器期
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第36問 下線部の子音の構音位置も構音様式も異なる組み合わせはどれか。
1. やま - はま
2. ばら - たら
3. つみ - すみ
4. こい - とい
5. まく - なく
第37問 日本語(共通語)の「ゲ」の子音として現れないのはどれか。
a.[ ]
b.[G]
c.[ ]
d.[ ]
e.[ ]
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第38問 「かんぜんちょうあく(勧善懲悪)」の音節数とモーラ数の適切な組み合わせはどれか。
1. 6 - 9
2. 6 - 8
3. 6 - 7
4. 5 - 9
5. 5 - 8
第39問 日本語(共通語)のイントネーションの性質として適切なのはどれか。
a.統語構造が反映される。
b.単語ごとに決まっている。
c.上昇したピッチは文末まで下がらない。
d.アクセントが関与しない。
e.ダウンステップが生じる。
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10
5. 11
第40問 ホルマント周波数に関連しないのはどれか。
1. 音速
2. 声道長
3. 口唇のすぼめ
4. 声帯の緊張
5. 舌の位置
第41問 「さざんか(山茶花)」の「さ」と「ざ」との子音の音響的違いはどれか。
1. 無声区間の有無
2. 摩擦区間の有無
3. 線スペクトル構造の有無
4. ホルマントの有無
5. アンチホルマントの有無
第42問 音声信号のデジタル音響分析で標本化周波数を選ぶとき考慮すべきものはどれか。
1. 信号振幅の最大値
2. 信号の基本周波数
3. 信号のホルマント周波数
4. 信号成分の最高周波数
5. 信号成分の最低周波数
第43問 正しいのはどれか。
1. 4ソーンの音の大きさは2ソーンの音の4倍である。
2. 1000Hz、100dBSPLの純音の大きさは1ソーンである。
3. 6フォン相当の音の大きさのレベルの上昇によって大きさは約2倍になる。
4. 4000Hz、10フォンの純音の大きさに相当する250Hzの純音の大きさのレベルは約30フォンである。
5. 250Hz、60フォンの純音の大きさは1000Hz、60dBSPLの純音の大きさと等しい。
第44問 同一形態素を含まない組み合わせはどれか。
1. 部屋 - 部室
2. 眼鏡 - 金物
3. 腐る - 臭い
4. 落ちる - 落とす
5. おずおず - 怖気づく(おじけづく)
第45問 ヲ格を要求する2項述語はどれか。
1. 渡る
2. もらう
3. 詳しい
4. 散歩する
5. 泣く
第46問 “[”が従属節の初めを示さないのはどれか。
1. 彼は彼女に[婚約を解消することを告げた。
2. 友人から[頼んでおいた資料をやっと受け取った。
3. 先週[旅行先で前から気になっていたバッグを買った。
4. 彼は[大学を卒業した直後にアメリカに留学した。
5. 生鮮食料品も[家族がネットで見つけた店で買っている。
第47問 最も早く出現するコミュニケーション行動はどれか。
1. 拍手などの身振りのまねをする。
2. あやされると声を出して笑う。
3. 大人が指差した物を見る。
4. 他者の興味を引くように物を提示する。
5. 「ちょうだい」と言われ持っている物を渡す。
第48問 社会保障制度の理念として誤っているのはどれか。
1. 法の下の平等
2. 生存権の保障
3. ノーマライゼーション
4. 婚姻の制限
5. 自己決定の実現
第49問 社会福祉関係の法規はどれか。
a.母体保護法
b.介護保険法
c.生活保護法
d.障害者自立支援法
e.健康増進法
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第50問 言語聴覚士の診療補助について誤っているのはどれか。
1. 機器を用いる一定の聴力検査
2. 聴性脳幹反応検査
3. 耳型の採型
4. 音声機能に係る検査
5. 生命維持装置の操作
第51問 誤っているのはどれか。
1. 手話は言語的コミュニケーションである。
2. 言語は無限に新しい表現を作り出すことができる。
3. 言語において能記と所記との間には必然性がある。
4. 言語の使用的側面を研究する分野を語用論という。
5. 広汎性発達障害では語用論的な問題を持つことが多い。
第52問 誤っているのはどれか。
1. 運動低下性構音障害は錐体外路の病変による。
2. 神経原性吃音は主に幼児期に発症する。
3. 失語症の半数以上が脳梗塞を原因とする。
4. 遂行機能障害は主に前頭前野の損傷で生じる。
5. 機能性構音障害は発達途上の構音の誤りが多数を占める。
第53問 正しいのはどれか。
a.折半法は信頼性を検証する方法である。
b.観察による評定が甘くなる傾向は天井効果と呼ばれる。
c.横断的研究では一定の研究対象者を継続的に追跡する。
d.過去の状況を現在の実態と関連づける研究は前方視研究である。
e.妥当性とは、尺度が測るべき概念を正しく測ることである。
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第54問 3歳6ヶ月の男児。言葉の遅れを主訴に来院。評価に適切でないのはどれか。
1. WPSSI知能診断検査
2. 〈S-S法〉言語発達遅滞検査
3. ITPA言語学習能力診断検査
4. 遠城寺式乳幼児分析的発達検査法
5. 遊戯聴力検査
第55問 前大脳動脈閉塞症で起こるのはどれか。
1. ブローカ失語
2. 伝導失語
3. 混合型超皮質性失語
4. ウェルニッケ失語
5. 超皮質性運動失語
第56問 誤っている組み合せどれか。
1. 反響言語 - 復唱
2. 語間代 - 保続
3. 発語失行 - 語漏
4. 心像性 - 具象語
5. 流暢性 - プロソディ
第57問 失語症の書字能力について正しいのはどれか。
1. 非利き手でも評価できる。
2. 書き取りができれば書称はできる。
3. 漢字が書ければ平仮名は書ける。
4. アラビア数字が書ければ漢数字は書ける。
5. 自分の氏名と住所が書ければ失書はない。
第58問 古典型失語症候群に分類する際に必須でない項目はどれか。
a.復唱
b.書称
c.読解
d.自発話
e.聴理解
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第59問 大脳機能の側性化の程度が最も強いのはどれか。
1. 記憶
2. 構成
3. 行為
4. 言語
5. 視覚認知
第60問 対話構造を導入した失語症の訓練法はどれか。
1. 刺激法
2. PACE
3. 遮断除去法
4. 機能再編成法
5. メロディック・イントネーション・セラピー
第61問 4歳の後天性小児失語症の評価に適さないのはどれか。
1. 標準抽象語理解力検査
2. 新版K式発達検査
3. ITPA言語学習能力診断検査
4. LCスケール
5. 〈S-S法〉言語発達遅滞検査
第62問 パペッツ(Papez)の回路に含まれないのはどれか。
1. 視床
2. 海馬
3. 脳弓
4. 乳頭体
5. 前脳基底部
第63問 相貌失認について正しいのはどれか。
1. 目がどれかわからない。
2. 人の頭と動物の顔の区別がつかない。
3. 口の動きが分からない。
4. 声を聞くと誰か分かる。
5. 病前から知っている人の顔は誰かわかる。
第64問 日常物品の使用訓練が有効な高次脳機能障害はどれか。
a.肢節運動失行
b.観念性失行
c.口舌顔面失行
d.使用行動
e.模倣行動
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第65問 ダウン症について誤っているのはどれか。
1. 伝音難聴の合併が多い。
2. 先天性心疾患が40~50%に合併している。
3. 21番染色体のトリソミーが95%を占める。
4. 筋緊張が高い。
5. 眼の屈折異常の合併が多い。
第66問 発達性ディスレキシア(発達性読み書き障害)で脳機能低下がみられることが多い部位はどこか。
1. a
2. b
3. c
4. d
5. e
第67問 ICD-10の精神遅滞の程度(IQ)で誤っているのはどれか。
a.境界域 - 75~84
b.軽度 - 50~74
c.中等度 - 35~49
d.重度 - 20~34
e.最重度 - 20未満
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第68問 誤っているのはどれか。
1. LCスケール - 形容詞の理解
2. 絵画語い発達検査 - 聴理解
3. 〈S-S法〉言語発達遅滞検査 - 単語の読み
4. 標準抽象語理解力検査 - 読解
5. 小学生の読み書きスクリーニング検査 - 1文字の読み
第69問 表のK-ABC心理・教育アセスメントバッテリーの結果の解釈で正しいのはどれか。
a.「13.ことばの読み」の得点が有意に低い。
b.「14.文の理解」が有意に高い。
c.「7.語の配列」が有意に高い。
d.継次処理が同時処理より有意に低い。
e.認知処理が習得度より有意に高い。
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第70問 誤っている組み合せはどれか。
1. KIDS - Kaufman Infant Development Scale
2. ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health
3. DAISY - Digital Accessible Information System
4. TOM - Theory of Mind
5. WFT - Word Fluency Test
第71問 アスペルガー障害の中学生の支援で適切なのはどれか。
a.構造化をなくす。
b.社会的ルールを視覚的に教える。
c.保護者に障害者手帳について情報的提供する。
d.周囲の人の気持ちを考えるように言いきかす。
e.相手の表情をよく見ながら話すように促す。
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第72問 正しい組み合せはどれか。
1. モデリング - 子どものことばを養育者が模倣
2. カウンセリング - 否定的態度
3. PECS - 身振り動作
4. ワークシステム - 構造化
5. リフレクティング - 子どものことばを文法的に拡大
第73問 5歳の女児。言語理解は単語レベルで、事物名称と人名は理解可能。動作語と大小・色名は理解不可。指導する2語連鎖で適切なのはどれか。
1. 対象+動作(みかんを食べる)
2. 動作主+動作(男の子が洗う)
3. 大小+事物(大きい車)
4. 色名+事物(赤い車)
5. 所有者+事物(女の子の車)
第74問 前言語期の言語発達障害児の保護者への助言で適切なのはどれか。
a.登園カバンを見せて行き先を予告する。
b.牛乳パックを見せて子どもにコップを取ってこさせる。
c.色名の理解を促す。
d.成人語音声の模倣を促す。
e.身振りの理解と表現を促す。
1. a、b、c
2. a、b、e
3. a、d、e
4. b、c、d
5. c、d、e
第75問 内視鏡を用いて行う検査法はどれか。
1. GRBAS評価
2. 最長発声持続時間
3. 発声時平均呼気流率
4. 喉頭ストロボスコピー
5. サウンドスペクトログラフィ
第76問 薬物治療の最も良い適応はどれか。
1. 声帯溝症
2. 声帯ポリープ
3. 喉頭肉芽腫
4. 喉頭横隔膜症
5. 反回神経麻痺
第77問 無喉頭音声について誤っているのはどれか。
1. 電気式人工喉頭は抑揚をつけやすい。
2. 笛式人工喉頭では肺からの呼気を用いる。
3. 食道発声では上部食道に取り込んだ空気を用いる。
4. 気管食道瘻発声のときには気管孔を閉鎖する。
5. 気管食道瘻発声の音源は新声門である。
第78問 構音障害の評価法で誤っている組み合せはどれか。
1. パラトグラフィ - 舌と口蓋の接触
2. 超音波検査 - 舌背の運動
3. 内視鏡検査 - 鼻咽腔閉鎖
4. 発話明瞭度検査 - 音の誤り
5. セファログラフィ - 口蓋咽頭後壁間距離
第79問 鼻咽腔構音になりやすい音はどれか。
a.イ列音
b.エ列音
c./ka/
d./pa/
e./sa/
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第80問 側音化構音の訓練に用いられるのはどれか。
a.鼻息鏡
b.バイトブロック
c.外鼻孔の閉鎖
d.語音弁別訓練
e.舌の脱力訓練
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第81問 構音障害の治療に用いないのはどれか。
1. Hotz床
2. 軟口蓋挙上装置
3. 舌接触補助装置
4. 口蓋閉鎖床
5. バルブ型スピーチエイド
第82問 進行口腔癌の切除後の再建に用いられるのはどれか。
a.咽頭弁
b.前腕皮弁
c.大胸筋皮弁
d.腹直筋皮弁
e.側頭筋弁
1. a、b、c
2. a、b、e
3. a、d、e
4. b、c、d
5. c、d、e
第83問 発声特徴抽出検査の評価内容にないのはどれか。
1. 声質
2. 話し方
3. 発話量
4. 話す速さ
5. 共鳴・構音
第84問 誤っているのはどれか。
1. 加齢に伴い喉頭は下垂する。
2. 嚥下反射の中枢は延髄にある。
3. 輪状咽頭筋は嚥下時に弛緩する。
4. 吸啜反射は3ヶ月頃から減弱する。
5. 嚥下機能は1歳頃までに完成する。
第85問 正しい組み合せはどれか。
1. 鼻咽腔閉鎖 - 改訂水飲みテスト
2. 声門閉鎖 - 反復唾液嚥下テスト
3. 食塊形成 - 嚥下圧検査
4. 喉頭挙上 - 嚥下内視鏡検査
5. 食道入口部開大 - 嚥下造影検査
第86問 気管切開を受けた患者について一般的に正しいのはどれか。
1. 喉頭閉鎖時に声門下圧を陽圧に維持できない。
2. 嚥下時の喉頭挙上が容易になる。
3. 嚥下障害患者には側孔のあるカニューレは避ける。
4. 嚥下障害患者にはカニューレへの一方弁装着は避ける。
5. 直接的嚥下訓練はカニューレのカフ圧を上げてから行う。
第87問 永久気管孔を必要とする嚥下障害の手術はどれか。
a.喉頭挙上術
b.輪状咽頭筋切断術
c.甲状軟骨形成術
d.気管食道吻合術
e.喉頭気管分離術
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第88問 吃音中核症状に含まれないのはどれか。
a.挿入
b.阻止
c.引き延ばし
d.音の繰り返し
e.語全体の繰り返し
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第89問 小児の滲出性中耳炎について正しいのはどれか。
1. 耳痛の訴えが強い。
2. しばしば鼓膜穿孔を生じる。
3. 中耳インピーダンスが低下する。
4. 小児の難聴の原因として最も多い。
5. 耳小骨が溶けて伝音難聴を生じる。
第90問 定型発達の1歳6ヶ月の聴性行動として適切でないのはどれか。
1. 隣の部屋の音に耳を傾ける。
2. 突然の大きな音に腕を突きだす。
3. テレビの音がするとサッと見る。
4. 「おいで」と言うと近寄る。
5. ささやき声で名前を呼ぶと振り向く。
第91問 4歳児で髄膜炎によって重度難聴発症。言語指導で優先するのはどれか。
1. 構音
2. 構文
3. 談話構成
4. 語彙獲得
5. コミュニケーション
第92問 聴覚障害幼児への話しかけで適切でないのはどれか。
a.ゆっくりと話す。
b.身振りを添えて話す。
c.音節で区切って話す。
d.耳元で大きな声で話す。
e.はっきりと正確に話す。
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第93問 図に示すオージオグラムについて、身体障害者福祉法による右耳の平均聴力レベル(四分法)はどれか。
1. 35dB
2. 40dB
3. 60dB
4. 65dB
5. 75dB
第94問 老人性難聴の主たる病態に関連しないのはどれか。
1. 血管条の萎縮
2. 有毛細胞の障害
3. 正円窓膜の硬化
4. 基底板の弾性の低下
5. らせん神経節細胞の減少
第95問 語音弁別検査について正しいのはどれか。
1. スピーチオージオグラムに正答率を記入し実線で結ぶ。
2. 語音を用いて閾値を測定する。
3. マスキングにはバンドノイズを用いる。
4. 明瞭度が100%になるまでリストを替えて実施する。
5. 1音ごとに下降法で呈示する。
第96問 進行性難聴を示さないのはどれか。
1. アッシャー症候群
2. 多発性硬化症
3. 先天性風疹症候群
4. ミトコンドリア脳筋症
5. ストレプトマイシンによる難聴
第97問 補聴器のノンリニア増幅について正しいのはどれか。
a.ボリューム操作回数を低減できる。
b.入力音に応じて出力音周波数を変化させる。
c.ハウリングを防止する。
d.騒音下の聞きとりを改善する。
e.入力音のレベルによって増幅度を自動的に変化させる。
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第98問 「補聴器適合検査の指針2010」に含まれないのはどれか。
1. 音場検査
2. 環境音の許容度の評価
3. 質問紙による適合評価
4. 雑音負荷での語音明瞭度検査
5. 補聴器の無入力時の雑音レベルの測定
第99問 リング6音の蝸牛内の受容について正しい組み合せはどれか。
a.eee[i] - 基底回転から中回転
b.shh[∫] - 基底回転
c.ooo[u] - 基底回転
d.mmm[m] - 基底回転
e.ahh[a] - 頂回転
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e
第100問 弱視になった聾(ろう)者に対して接近手話(弱視手話)を使用する場合、適切でない組み合せはどれか。
a.話者との距離 - 近いほど良い。
b.表情 - 大きいほど良い。
c.口唇の動き - 大きいほど良い。
d.手指の位置 - 見やすい場所で行う。
e.手の動き - 大きく動かす。
1. a、b
2. a、e
3. b、c
4. c、d
5. d、e