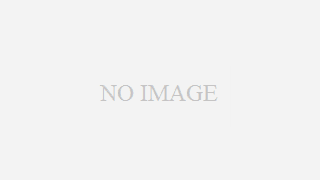 リハビリ・医療
リハビリ・医療 とろみの必要性について
とろみの必要性について
口から食べる機能が障害されると、一般的に水分やお茶、味噌汁のようなものが上手に飲めなくなります。水のようにサラサラした粘度の低い液体は、動きが速く、口の中で広がりやすいため、誤って気管に入ってしまう場合がありま...
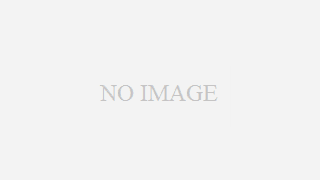 リハビリ・医療
リハビリ・医療  リハビリ・医療
リハビリ・医療 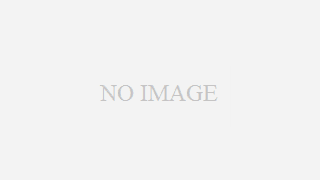 リハビリ・医療
リハビリ・医療 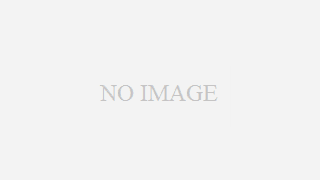 リハビリ・医療
リハビリ・医療 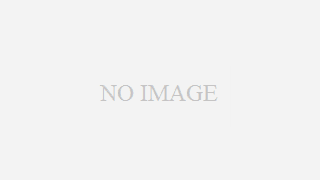 リハビリ・医療
リハビリ・医療 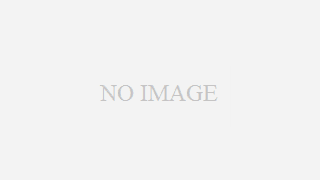 リハビリ・医療
リハビリ・医療 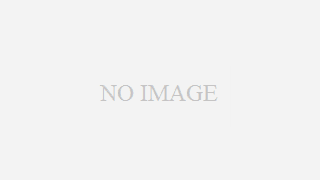 リハビリ・医療
リハビリ・医療 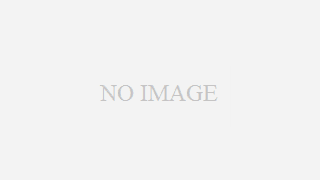 リハビリ・医療
リハビリ・医療 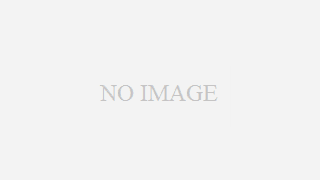 リハビリ・医療
リハビリ・医療 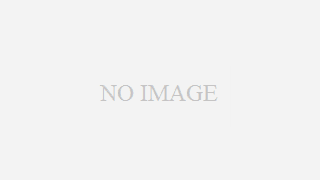 リハビリ・医療
リハビリ・医療