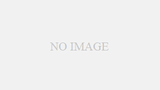第101問 言語聴覚障害学の歴史について正しいのはどれか。
- 我が国では1930年代に言語治療教室が設置された。
- 言語聴覚障害学はアメリカにおいて2世紀に近い歴史を有している。
- ヨーロッパでは19世紀はじめに音声言語医学の国際学会が創立された。
- 我が国はアメリカと比べ言語聴覚障害学の発展は約10年の遅れがある。
- 我が国での4年制大学における言語聴覚士の本格的な養成は、1990年代に入ってから着手された。
解答例<5>
第102問 原因不明で非流暢性を示すのはどれか。
- 言語発達遅滞
- 機能性構音障害
- 吃音
- 失語症
- 運動障害性構音障害
解答例<3>
第103問 誤っているのはどれか。
a.言語聴覚障害の多くは完全に治癒する。
b.言語障害の重症度は言語症状の程度で決まる。
c.言語発達障害には原因不明のものが多い。
d.拡大代替コミュニケーション・アプローチは残存機能に焦点を合わせる。
e.前言語的コミュニケーションの段階は言語発達の基礎となる。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<1>
第104問 言語聴覚障害について正しいのはどれか。
a.自分の障害の状態を人に伝えることが難しい。
b.知的障害や人格障害など別の障害に誤解される。
c.教科学習の阻害要因となる。
d.思考の発達の阻害要因とならない。
e.読みの障害は言語聴覚障害に含まれない。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<1>
第105問 言語診断について正しいのはどれか。
a.患者の過去のデータは診断上重要ではない。
b.障害に対する患者自身の評価は必要な情報である。
c.言語症状の発生原因について判断することが目的の一つである。
d.障害の有無を判定することを鑑別診断という。
e.診断は常に治療に先行する。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<3>
第106問 正しい組み合せはどれか。
- 聴覚的把持 - 被刺激性検査
- 内耳機能 - ティンパノメトリー
- 構音動態 - パラトグラフィ
- 器質性構音障害 - 語音明瞭度検査
- 表出語量 - 絵画語彙発達検査
解答例<3>
第107問 言語治療について正しいのはどれか。
a.訓練段階毎にゴール設定を行う。
b.訓練法について定期的評価を行う。
c.原因疾患が確定してから開始する。
d.改善に対する家族の意欲に基づいて終了時期を決定する。
e.刺激法は基本的技法である。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<2>
第108問 挨拶のとき「おはようございます、ます、ます、ます」と止まらないのはどれか。
- 残語
- 語間代
- 錯語
- 再帰性発話
- 同語反復
解答例<2>
第109問 ブローカ領域について正しいのはどれか。
a.左下前頭回三角部
b.左下前頭回弁蓋部
c.左下前頭回眼窩部
d.左中前頭回後方部
e.左前頭葉内側面
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<1>
第110問 ウェルニッケ領域の中核はどれか。
a.左上側頭回後方
b.左中側頭回後方
c.左下側頭回後方
d.左横回
e.左側頭平面
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<1>
第111問 ウェルニッケ失語の特徴でないのはどれか。
a.発語障害
b.理解障害
c.構音障害
d.視空間障害
e.記憶障害
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<5>
第112問 伝導失語の病巣はどれか。
a.左下前頭回後方
b.左下側頭回中央部
c.左中心回下方
d.左縁上回
e.左半球弓状束
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<5>
第113問 左角回病巣で起こりやすいのはどれか。
a.読みの障害
b.呼称の障害
c.聴理解の障害
d.復唱の障害
e.書字の障害
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<2>
第114問 言語性検査のみによって構成されているのはどれか。
a.レーブン色彩マトリックス検査
b.コース立方体検査
c.ウェクスラー成人知能検査
d.改訂長谷川式簡易知能評価スケール
e.三宅式記銘力検査
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<5>
第115問 即時記憶の検査はどれか。
- 論理的記憶検査
- 対連合学習検査
- 聴覚言語性学習検査
- 迷路学習検査
- 数唱検査
解答例<5>
第116問 前頭側頭型痴呆の初発症状はどれか。
- 前向性健忘
- 人格変化
- 道順障害
- 計算障害
- 構成障害
解答例<2>
第117問 地誌的見当識障害の症状はどれか。
a.熟知した風景を認知できない。
b.自宅の住所を言えない。
c.病院名を覚えられない。
d.建物の用途がわからない。
e.道順を覚えられない。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第118問 症状と病巣との組み合せで頻度が低いのはどれか。
a.構成障害 - 左半球損傷
b.地誌的見当識障害 - 左半球損傷
c.観念運動失行 - 右半球損傷
d.肢節運動失行 - 右半球損傷
e.相貌失認 - 右半球損傷
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<3>
第119問 一過性全健忘で主に障害されるのはどれか。
a.即時記憶
b.近時記憶
c.遠隔記憶
d.意味記憶
e.手続記憶
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<3>
第120問 右半球損傷の慢性期にみられやすい症状はどれか。
- 半側空間無視
- 半側身体失認
- 運動無視
- 病態失認
- 錯乱状態
解答例<1>
第121問 我が国で現在用いられている失語症検査に共通の特徴はどれか。
a.症候の鑑別
b.反応の6段階評価
c.タイプの数量分類
d.重症度の尺度化
e.継時的変化の把握
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第122問 誤っている組み合せはどれか。
- 重度失語症検査 ーー 非言語的記号能力
- トークンテスト ーー 聴覚的理解
- 失語症構文検査 ーー 語順ストラテジー
- 音韻抽出検査 ーー 音の系列化
- CADL ーー コミュニケーションレベル
解答例<4>
第123問 失語症に合併しやすい障害はどれか。
a.片麻痺
b.同名半盲
c.観念運動失行
d.環境音失認
e.半側無視
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<1>
第124問 失語症について正しいのはどれか。
a.拡大代替コミュニケーション訓練は、人工的な符号系の獲得を目標とする。
b.呼称障害の基底にある障害は、意味レベルか音韻レベルかに明確に分類できる。
c.刺激・促通法は失語症を言語機能の「抑制」と考える。
d.Schuellの刺激法でいう「適切な刺激」の「適切」レベルとは、患者にとって容易な課題レベルである。
e.文字言語訓練では、音声言語改善のための介在手段として文字言語を利用する。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<5>
第125問 失語症訓練法について誤っている組み合せはどれか。
- 刺激・促通法 ーー 感覚刺激の反復
- 機能再編成法 ーー キーワード法による仮名文字訓練
- 認知神経心理学的アプローチ ーー 治療モデルの提示
- PACE ーー 情報の送り手と受け手との対等な役割分担
- AAC ーー 非言語的コミュニケーション予段の使用訓練
解答例<3>
第126問 失語症の言語訓練効果について正しいのはどれか。
a.発症後1か月以内の訓練で得られた改善は自然治癒による改善と区別し難い。
b.訓練効果は非訓練項目には般化しない。
c.訓練効果をみるには訓練を受けた群と受けない群の成績を比較すればよい。
d.単一被験者治療実験法は言語訓練の効果の定量的測定を可能にする。
e.言語表出面の改善は訓練効果であることが多い。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<3>
第127問 後天性小児失語症について正しいのはどれか。
a.発症前の言語発達レベルまでの回復は早い。
b.言語習得の長期予後は良好である。
c.集中力や記銘力の低下を示す例は少ない。
d.原因疾患の第一位は脳血管障害である。
e.損傷をもつ脳で言語を習得しなければならない。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第128問 正しいのはどれか。
a.80dB以上の難聴を放置すれば正常言語は発達しない。
b.40dB以下の難聴では言語発達は遅れない。
c.2KHz以上の聴力障害では構音障害を生じない。
d.2KHz以上の聴力が正常でも韻律障害を生じる。
e.250Hz以下の聴力が正常な場合は韻律障害はない。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第129問 誤っている組み合せはどれか。
- 後天性失語症 ーー 巣症状
- 発達性発語失行 ーー 小脳障害
- 運動障害性構音障害 ーー 仮性球麻痺
- 構音障害 ーー 難聴
- 学習障害 ーー 認知障害
解答例<2>
第130問 補聴器の適応でないのはどれか。
a.内耳性難聴
b.両側側頭葉損傷
c.ランドー・クレフナー症候群
d.心因性難聴
e.重度知的障害を合併する難聴
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<4>
第131問 誤っている組み合せはどれか。
- 運動性言語発達遅滞 ーー 発話の障害
- 小児失語症 ーー 言語障害
- ろうあ者の手話 ーー 非言語的コミュニケーション
- 純粋語聾 ーー 語音弁別能の障害
- 口蓋裂 ーー 構音・共鳴障害
解答例<3>
第132問 スクリーニングで難聴がないと判断できるのはどれか。
a.新生児で音刺激に対しモロー反射が出る。
b.幼児で紙もみ音に反応する。
c.クリックに対し聴性脳幹反応(ABR)が出現する。
d.ささやき声検査で100パーセント聴き取れる。
e.テレビの好きなコマーシャルを聞いて見にくる。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例
第133問 3か月児があやされても音声に無反応な場合の解釈はどれか。
a.情緒障害の疑いがある。
b.聴覚障害の疑いがある。
c.広汎性発達障害の疑いがある。
d.重度知的障害の疑いがある。
e.人見知り反応の可能性かある。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<4>
第134問 言語発達検査について適切なのはどれか。
- 実施手続きを子どもの発達レベルに合わせて修正する。
- 子どもの反応を促すために正反応をほめて励ます。
- 子どもの正反応が得られるまで繰り返し提示する。
- 子どもの関心に合わせて検査手続きを修正する。
- 検査手引の作成者の意図を理解する。
解答例
第135問 4歳から施行できる検査はどれか。
a.絵画語彙発達検査
b.グッドイナフ人物画検査
c.WISC-R知能診断検査
d.コース立方体検査
e.ITPA言語学習能力診断検査
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<2>
第136問 AACによるコミュニケーション指導に必要なのはどれか。
a.肯定・否定の対比概念の理解
b.指さしができる上肢コントロール
c.座位が保てる躯幹のコントロール
d.平仮名文字の読みが可能
e.他者とのコミュニケーション意欲
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第137問 正しいのはどれか。
a.摂食指導に姿勢の問題を考慮する必要がある。
b.重度障害児の摂食指導にはストローの早期導入が有効である。
c.摂食指導では生活年齢に応じた食事の献立が基本である。
d.摂食機能の発達は構音機能の発達に関係する。
e.摂食指導には食材や調理方法の配慮が必要である。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<3>
第138問 子どもの感覚運動体験について正しいのはどれか。
a.子どもが物に触ってなめる行為は新生児期からみられる。
b.認知発達が未熟な子どもは無意図的に探索を繰り返す。
c.肢体不自由児と健常児とでは差がない。
d.前言語期では言語的意味形成の基盤となる。
e.前言語期には大人の意味づけが大切である。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<5>
第139問 助詞指導について適切でないのはどれか。
a.動作主・動作対象・動作方向の理解に留意する。
b.実際の活動内容を言語化し自然な助詞の使用例を示す。
c.語彙指導の前に行う。
d.格助詞と終助詞は同時に教える方がよい。
e.語順ストラテジーがみられてから助詞を教える。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<4>
第140問 平仮名の単文字は読めても単語は読めない要因はどれか。
a.知的発達の遅れ
b.視力障害
c. 視力障害
d.単語の聴覚イメージの未発達
e.音韻分解・抽出能力の未発達
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<3>
第141問 広汎性発達障害について正しいのはどれか。
- 自閉症に含まれる。
- 正常知能を有することはない。
- 自己中心的行動特徴を有する多動児である。
- 語用の発達が遅れる。
- 社会的相互作用の問題は少ない。
解答例<4>
第142問 学習障害について正しいのはどれか。
a.個人内で発達の諸領域に凹凸を示す。
b.難聴による学習困難も含まれる。
c.知的発達が遅れる。
d.成人期に問題を残すことは少ない。
e.高次機能の発達障害である。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第143問 ことばの遅れがある1歳3か月の男児について、精神遅滞の可能性を示唆するのはどれか。
- 1歳2か月で歩き始めた。
- 発語が1、2語である。
- 色の名前がわからない。
- ごっこ遊びをしない。
- 積木を与えてもなめてばかりいる。
解答例<5>
第144問 幼児期の自閉症にみられる行動はどれか。
- 決まった手順を好む。
- 動作模倣をする。
- 関心を自分の方に向けようとする。
- ふり遊びをする。
- 視覚刺激より聴覚刺激を好む。
解答例<1>
第145問 健常な2歳児にみられない行動はどれか。
- 二語文をいう。
- 「なに」の質問行動をする。
- 「どうぶつ」、「のりもの」などの上位概念がわかる。
- 動詞の活用形が使える。
- 絵本を読んであげると喜ぶ。
解答例<3>
第146問 自閉症児がコマーシャルの商品名をよく覚える行動の基礎にある問題はどれか。
- 語用
- 統語
- 構音
- 意味の領域
- 言葉を聞く頻度
解答例<1>
第147問 言語聴覚士の対応として誤っているのはどれか。
- 家族に対し言語とコミュニケーションの発達の状況を伝える。
- 子どもの情報を直ちに所属学校長に報告する。
- 担当医に子どもに関する情報を照会する。
- 子どもの進路相談に応じる。
- 家族が子どもの障害を理解するための援助を行う。
解答例<2>
第148問 声のピッチを上げるのはどれか。
- 胸骨舌骨筋
- 後輪状披裂筋
- 披裂筋
- 輪状甲状筋
- 側輪状被裂筋
解答例<4>
第149問 音声治療・指導について誤っている組み合せはどれか。
- 痙攣性音声障害 ーー pushing exercise
- 急性声帯炎 ーー voice rest
- 反回神経麻痺 ーー pushing exercise
- ポリープ様声帯 ーー no smoking
- 変声障害 ーー Kayser-Gutzmann法
解答例<1>
第150問 反回神経について正しいのはどれか。
- 輪状甲状筋は支配しない。
- 舌咽神経の分枝である。
- 右側は左側より長い。
- 左側は鎖骨下動脈をまわって上行する。
- 右側は大動脈弓をまわって上行する。
解答例<1>
第151問 口蓋裂術後の評価法でないのはどれか。
- 鼻咽腔ファイバースコピー
- エックス線咽頭側壁撮影
- パラトグラフィ
- 口腔内圧測定
- 唾液流量測定
解答例<5>
第152問 嚥下障害の治療・訓練において正しいのはどれか。
- 直接的嚥下訓練における代償的アプローチにおいて、1回の嚥下量は問題ではない。
- 間接的嚥下訓練ではぺースト状の食材から開始する。
- 嚥下訓練を根気よく行うことで完治する。
- 輪状咽頭筋切断術が用いられる。
- 気管カニューレは嚥下訓練上問題とならない。
解答例<4>
第153問 音声訓練に関係しない協調動作はどれか。
- あくび
- 咳
- ため息
- 笑 い
- うがい
解答例<5>
第154問 機能性構音障害の訓練法に利用されない感覚はどれか。
- 運動覚
- 触覚
- 視覚
- 聴覚
- 温度覚
解答例<5>
第155問 正しいのはどれか。
- 粘膜下口蓋裂の確定診断は手術後に決まる。
- 先天的に軟口蓋の運動低下を示す疾患はない。
- 口蓋裂手術後の硬口蓋の形態は構音に影響しない。
- 咽頭弁手術では鼻呼吸に配慮する必要はない。
- 口蓋裂には惨出性中耳炎の合併が多い。
解答例<5>
第156問 舌癌の術後で正しいのはどれか。
a.舌の容量と可動性とが発話明瞭度を左右する。
b.発話明瞭度が自然に改善することはない。
c.咀嚼・嚥下障害の合併は稀である。
d.単語検査、会話明瞭度検査で訓練の適応を決める。
e.構音訓綾は代償構音の習得も含む。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<3>
第157問 正しいのはどれか。
a.多発性硬化症では混合性構音障害になる。
b.小脳変性症では運動過多性構音障害が出現する。
c.構音に関係する末梢神経の核は延髄に集中する。
d.筋疾患は運動障害性構音障害の原因とはならない。
e.運動低下性構音障害は錐体外路系の病変で起こる。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第158問 左片麻痺患者について正しいのはどれか。
- 右側の閉眼が困難である。
- 右側の口角部からの流涎がある。
- 口唇を突き出させると左側に偏位する。
- 安静時の舌は左側に偏位している。
- 軟口蓋の挙上範囲は左側が右側より大きい。
解答例<4>
第159問 運動障害性構音障害の訓練について誤っているのはどれか。
- 呼気の持続延長を図る訓練は発話呼吸パターンの再獲得につながる。
- 痙性構音障害の訓練では筋の緊張状能のコントロールが不可欠である。
- 構音訓線では音連続課題によるわたりの訓練が重要である。
- 失調性構音障害では発話運動の不規則性を抑制する。
- 高度鼻咽腔閉鎖機能不全は訓練で正常化する。
解答例<5>
第160問 鼻咽腔閉鎖機能不全を起こさないのはどれか。
a.口蓋扁桃肥大
b.口蓋裂
c.軟口蓋麻痺
d.軟口蓋短小
e.高位口蓋
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第161問 吃音について正しいのはどれか。
- 男児に多い。
- 遺伝的素因は関与しない。
- 発吃の時期は学童期に集中する。
- 幼児期の発症は自然に治癒する率が低い。
- 心理的ショックが関係することはない。
解答例<1>
第162問 嚥下時の喉頭挙上に関与するのはどれか。
a.胸骨舌骨筋
b.胸骨甲状筋
c.胸鎖乳突筋
d.甲状舌骨筋
e.オトガイ舌骨筋
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<5>
第163問 嚥下時の喉頭防御機能で誤っているのはどれか。
- 声門が閉鎖する。
- 裂喉頭蓋ヒダが絞扼する。
- 鼻咽腔が閉鎖する。
- 喉頭は前上方へ挙上する。
- 嚥下時に呼吸は停止する。
解答例<2>
第164問 咽頭食道造影検査で異常な所見はどれか。
- 造影剤の鼻咽腔への逆流
- 造影剤の梨状窩での残留
- 喉頭下降後の造影剤の喉頭内への流入
- 後上方への喉頭挙上
- 1椎体間の喉頭挙上
解答例<5>
第165問 嚥下訓練におけるアイスマッサージ法の目的はどれか。
- 咽頭の収縮
- 咽頭期嚥下の誘発
- 輪状咽頭筋の弛緩
- 喉頭の閉鎖
- 鼻咽腔の閉鎖
解答例<2>
第166問 嚥下障害の治療法でないのはどれか。
- 口蓋垂口蓋形成術(UPPP)
- 声帯正中固定術
- 喉頭挙上術
- 喉頭全摘出術
- 喉頭気管分離術
解答例<1>
第167問 下顎を下方に引く嚥下訓練の目的はどれか。
a.喉頭挙上力の改善
b.咽頭収縮力の改善
c.気道の防御
d.舌根の牽引
e.食道入口部の収縮
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<4>
第168問 食道音声と関連のないのはどれか。
- 新声門
- 空気の逆流
- 腹圧
- 声門閉鎖
- 子音注入法
解答例<4>
第169問 吃音の発話症状はどれか。
- 失声
- 保続
- ジャルゴン
- 錯語
- 阻止
解答例<5>
第170問 幼児の吃音の特徴でないのはどれか。
- 改善しやすい。
- 環境の影響が小さい。
- 吃音音歴が短い。
- 進展が遅い。
- 変動が大きい。
解答例<2>
第171問 「机」を[t∫ukue]と言った場合、正しいのはどれか。
- 破擦音が破裂音化している。
- 破裂音が被擦音化している。
- 破擦音が置換されている。
- 構音様式が誤っている。
- 子音が歪んでいる。
解答例<3>
第172問 舌切除後の訓練について誤っているのはどれか。
a.舌運動の促進を主として行う。
b.構音訓練は術後6か月を過ぎてから開始する。
c.筆談の訓練を行う。
d.流涎の処理法を指導する。
e.構音訓練の効果について説明する。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<1>
第173問 側音化構音について誤っているのはどれか。
a.呼気の放出方向が異常である。
b.下顎の偏位を伴う。
c.口角の偏位を伴う。
d.ウ列音に出現しやすい。
e.咬咳合異常が原因である。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<5>
第174問 3歳児が「はさみ」を[aami]と言った場合、誤っているのはどれか。
a.誤りのタイプは省略と置換である。
b.難聴の疑いがある。
c.構音器官の評価が必要である。
d.言語発達の評価が必要である。
e.幼児音と考えられる。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第175問 日本人の成人女性の平均話声位はどれか。
- 100 Hz前後
- 200 Hz前後
- 300 Hz前後
- 400 Hz前後
- 500 Hz前後
解答例<2>
第176問 鼻咽腔閉鎖機能不全の代償としての異常構音でないのはどれか。
a.咽頭摩擦音
b.口蓋化構音
c.側音化構音
d.咽頭破裂音
e.声門破裂音
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<3>
第177問 聴覚障害児に対する補聴の方法でないのはどれか。
- 補聴器
- 鼓室形成術
- 人口内耳
- スピーチエイド
- 視覚刺激
解答例<4>
第178問 内耳機能検査法でないのはどれか。
- SISI検査
- ABLB検査
- ティンパノメトリー
- 耳小骨筋反射検査
- 自記オージオメトリー
解答例<3>
第179問 聴性脳幹反応検査が適用されないのはどれか。
- 先天性難聴
- 心因性難聴
- 滲出性中耳炎
- 聴神経腫瘍
- 皮質性難聴
解答例<3>
第180問 聴性行動反応聴力検査(BOA)で正しいのはどれか
a.音源を探索しようとする反応を用いる。
b.検者は被検児から見えないようにする。
c.スピーカは被検児の正面に1個置く。
d.刺激音はクリック音を用いる。
e.6か月の健聴児の平均反応閾値は約10dBである。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<1>
第181問 遊戯聴力検査で正しいのはどれか。
- 驚愕反射を利用した検査法である。
- 適応年齢は1-2歳である。
- 音と同時に音が出た方の人形を照らす。
- 音が聞こえたら玩具で簡単な遊戯をさせる。
- 3歳の健聴児の平均反応閾値は50-60dBである。
解答例<4>
第182問 補充現象が陽性となるのはどれか。
- 伝音性難聴
- 内耳性難聴
- 後迷路性難聴
- 皮質性難聴
- 機能性難聴
解答例<2>
第183問 自記オージオメトリーで正しいのはどれか。
a.検査結果は5つの型に分類される。
b.正常耳では持続音と断続音による閾値が同一レベルにある。
c.補充現象のある耳では断続音記録で振幅が縮小する。
d.持続音記録で一過性の閾値上昇を認める時は内耳性難聴が疑われる。
e.断続音記録よりも持続音記録の方で閾値が低い時は機能性難聴が疑われる。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<2>
第184問 感音性難聴がみられないのはどれか。
- 先天性風疹症候群
- 先天性梅毒
- Alport症候群
- Pendred症候群
- Treacher Collins症候群
解答例<5>
第185問 難聴が反復・消長するのはどれか。
- 耳硬化症
- 突発性難聴
- メニエール病
- 騒音性難聴
- 真珠腫性中耳炎
解答例<3>
第186問 小児人工内耳の適応でないのはどれか。
- 重度の聴覚障害
- 重度の知的障害
- 髄膜炎による蝸牛骨化
- 内耳奇形
- 3歳末満の患児
解答例<2>
第187問 小児人工内耳のリハビリテーションで誤っているのはどれか。
- 音入れでCレベル以上の刺激は避ける。
- 遊びの中で話を聞く、会話をする環境を作る。
- 視覚言語の使用を禁じる。
- 先天聾の音入れでは患児の表情に注目する。
- 両親や教育関係者の協力が必要である。
解答例<3>
第188問 人工内耳について正しいのはどれか。
- 装用者は定期的な画像検査が必要である。
- 人工内耳の手術費用には医療保険が適用されない。
- 人工内耳と補聴器の同時装用は不可能である。
- 語音弁別能の良好例は人工内耳の適応とならない。
- 人工内耳の術後には耳鳴が増悪する。
解答例<4?>
第189問 補聴器の特徴として誤っているのはどれか。
- 挿耳形補聴器はハウリングが起こりやすい。
- 耳掛形補聴器は眼鏡の邪魔になる。
- 箱形補聴器は他機種より高出力を得やすい。
- 耳掛形補聴器は汗に強い。
- 箱形補聴器は衣擦れ音が聞こえやすい。
解答例<4>
第190問 補聴器の特性測定に使用しないのはどれか。
- スピーチプロセッサ
- 密閉型擬似耳
- 2?カプラ
- 測定用マイクロホン
- 無響箱
解答例<1>
第191問 最重度難聴児の発声・発語で誤っているのはどれか。
- 声帯浮腫を伴うことが多い。
- 甲高い声で話す。
- 正しいりズムで発音できる。
- 異常な声のピッチは人工内耳で改善する。
- 年長児より年少児の方が人工内耳による構音改善がみられる。
解答例<1>
第192問 誤っているのはどれか。
a.生後2-3か月の乳児は楽器音の方に振り向いて反応する。
b.難聴児の聴覚発達は母子関係の関与が大きい。
c.難聴乳幼児に補聴器を装用すると発声・発話量は増える。
d.難聴児の語音聴取能低下と構音の歪みとは関わりがある。
e.一側性の重度難聴児は言語発達遅滞を伴いやすい。
- a、b
- a、e
- b、c
- c、d
- d、e
解答例<2>
第193問 聴覚障害による影響を受けにくいのはどれか。
- 言語の発達
- コミュニケーション関係の成立
- 運動の巧徴性の発達
- 学習の達成
- 社会性の成熟
解答例<3>
第194問 聴覚障害児の発達保障に関する両親指導で誤っているのはどれか。
- 指導手順と発達の見通しを伝える。
- 補聴や聴こえについての可能性と限界を伝える。
- 難聴児を育てた経験のある他の親を紹介する。
- 聴能訓練中は家庭での手話の使用を禁じる。
- 社会生活を送っている聴覚障害者を紹介する。
解答例<4>
第195問 補聴器装用上の留意事項として正しいのはどれか。
a.感音難聴者より伝音難聴者の方が補聴器の効果が得られやすい。
b.FM補聴器の使用によってS/N比の改善が期待できる。
c.幼少児には耳形耳栓は不要である。
d.リニア補聴器はノンリニア補聴器ほど頻回に音量調整を行う必要はない。
e.耳漏がある場合は挿耳形補聴器を使用しない。
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<2>
第196問 聴覚障害者がテレビやラジオを視聴するときに利用しないのはどれか。
- 字幕放送デコーダー
- 字幕入りビデオライブラリー
- 磁気誘導ループ
- 携帯用信号装置
- ヘッドホン
解答例<4>
第197問 補聴器を装用しても聴きとりにくいのはどれか。
a.遠くからの呼びかけ
b.講演会や会議などでの話
c.テレビがついている時の会話
d.女性の声
e.ループを通した声
- a、b、c
- a、b、e
- a、d、e
- b、c、d
- c、d、e
解答例<1>
第198問 成人聴覚障害者について誤っているのはどれか。
- 聴覚障害が生じた年齢によって援助内容が異なる。
- 日本手話を使う人には若年期失聴者が多い。
- 成人期失聴者は補聴器に対する満足度が高い。
- 要約筆記通訳があると集会や講演会に参加しやすい。
- ノートテーカーとは個人に対する情報保障である。
解答例<3>
第199問 中途失聴者への初期段階の指導として適切でないのはどれか。
- カウンセリング
- コミュニケーションストラテジーの導入
- 補聴器適合・調整
- 字幕放送デコーダーの設置
- 手話教室への紹介
解答例<5>
第200問 視覚聴覚二重障害者について誤っているのはどれか。
- コミュニケーションの保障かないと周囲から孤立してしまう。
- 幼い頃からの盲ろう障害者は言語発達の問題が大きい。
- 聾の人が成人して盲となった時はコミュニケーション手段として主に指点字を使っている。
- 手話や点字など多様なコミュニケーション手段をもった通訳が必要である。
- 点字を使う二重障害者には携帯用会話補助器としてブリスタがある。
解答例<3>