聴覚障害を調べる検査法をまとめました。きこえの検査は年齢や調べる部位によって様々な種類があります。ここでは代表的な検査法を記載しておりますので参考にしてください。
標準純音聴力検査
一般的に「聴力検査」、「きこえの検査」と云えばこの検査のことを指します。オージオメーターという機器を用いて、周波数毎に聴こえる音のレベルを調べます。気導と骨導の検査が可能。

語音聴力検査
「あ」、「か」などの言葉がどの程度聞き取れるかを調べる検査です。耳の聞き取り能力を調べるほかに、補聴器を着けての音の聞き取り能力を調べることもできます。

聴性行動反応検査(BOA)
乳児初期を対象に行う聴覚検査です。音の出るおもちゃ(鈴や太鼓など)や携帯用オージオメータを使用し、乳児の振り向く・泣きだす・驚くなどの音への反応でおおまかな聴こえの程度を調べます。
条件詮索反応聴力検査(COR)
1~2歳の幼児を対象に行う聴覚検査です。左右にスピーカーを設置して、片方のスピーカーから音を出し、幼児がその音の鳴る方向を探す反応(詮索反応)から聴力を調べます。幼児がスピーカーの方向を向いたときに、人形や光で興味を引きながら行うことで検査結果の正確性が高まりますが、両耳一緒に調べるので左右それぞれの耳の聴力値は測れません。
ピープショウ検査(peep show test)
2~3歳の幼児を対象に行う聴覚検査です。音が聴こえている間、ボタンを押すとおもちゃが見える機器を使用して行う検査で、スピーカーによる両耳一緒の検査とヘッドホンによる片耳ずつの検査ができます。音が鳴らない間にボタンを押してもおもちゃは見えず、音が鳴るときだけボタンを押すということを学習しながら行うことで検査結果の正確性が高まります。
遊戯聴力検査(Play Audiometry)
3歳以上の児童を対象に行う聴覚検査です。音が聞こえたらおもちゃを動かしたりして、こどもの興味を引きながら行う検査で、ヘッドホンにより片耳ずつ聴力を調べることができます。おもちゃは、おはじきや積み木、ビー玉、パズルなど児童の興味を引くものであれば何でもかまいません。『音が聞こえたときだけおもちゃで遊べる』ということが学習できれば、2歳前後からでも検査ができます。
耳音響放射検査(OAE)
耳の中から外に向かってエコーが返ってくる現象(耳音響放射)を利用して、内耳(特に外有毛細胞)の状態を調べる検査です。イヤホンを耳に入れて、音を聞くだけで内耳の反応を検査することができます。簡便で短時間で検査でき、本人の反応も要さないため、新生児聴覚スクリーニング検査にも応用されています。
※新生児聴覚スクリーニングとは、新生児を対象に聴力が正常かどうかを判断するために行うスクリーニング検査です。
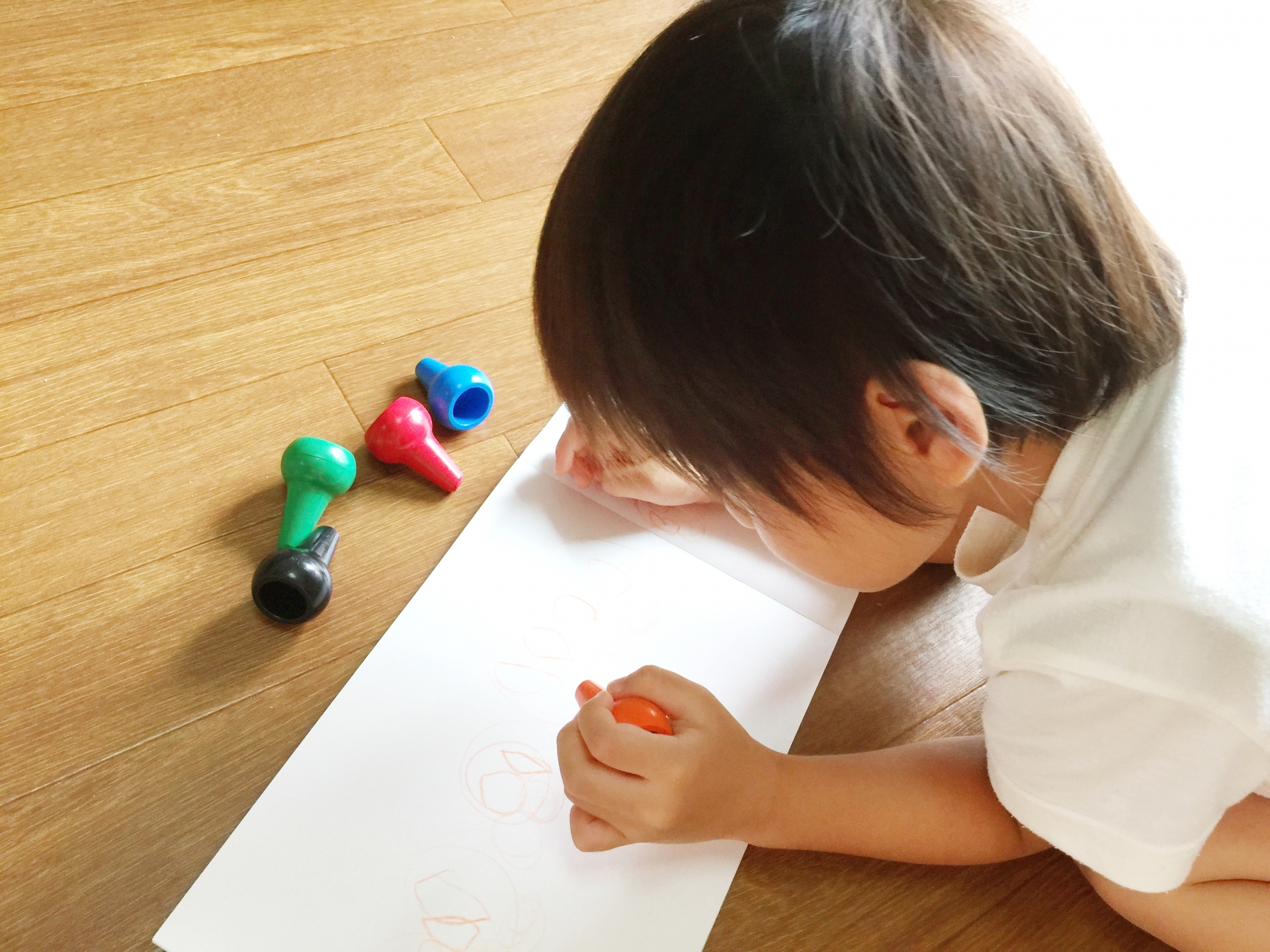
ABR、ASSR
本人による自覚反応ではなく、脳波を利用した他覚的反応を元に聴覚を調べる検査です。本人の自覚的な反応を必要としないので、赤ちゃん、幼小児、知能の低下があって普通の検査ができない時、および脳腫瘍による難聴の診断に極めて有用です。また、脳波の波形を分析することで、難聴の程度、障害部位を診断することも可能です。代表的な検査法には、聴性脳幹反応検査(ABR)と聴性定常反応検査(ASSR)があります。

自記聴力検査
自記オージオメトリーとも呼ばれる検査法です。ヘッドホンを耳に当て、器械から継続的に検査音が発せられるので、聞こえてきたらスイッチを押し、聞こえなくなったら離し、また聞こえてきたら押す。これを何度も繰り返して聴力を調べます。検査音は連続音(ピーーーー)と断続音(ピッピッピッ)で行い、内耳の機能や聴神経の働きを調べます。
SISI検査(内耳機能検査)
ヘッドホンから一定の間隔で20回音を聞き、音が大きくなったことに気づいたら知らせるという検査です。20回のうち何回気づいたかを%で表わします。感音性難聴にみられる補充現象(リクルートメント現象)の有無を調べることができます。
ティンパノメトリー
子供に多く見られる滲出性中耳炎は、中耳腔に液体が溜まる中耳炎ですが、これを診断するにはティンパノグラムと呼ばれる検査が大変有用です。この検査では、外耳道の入口に耳栓をして検査します。この耳栓の中には、小さいスピーカーとマイクロフォン、それと空気の圧力を送るポンプが入っています。ポンプによって外耳道の圧力を変え、その時、音がどのように鼓膜に伝わるかを調べる検査です。
耳小骨筋反射検査(SR)
90~100dB以上の大きな音が聞こえるとアブミ骨筋が収縮し耳を守る反射を利用した検査です。アブミ骨筋は顔面神経支配のため、顔面神経麻痺の検査にも利用されます。


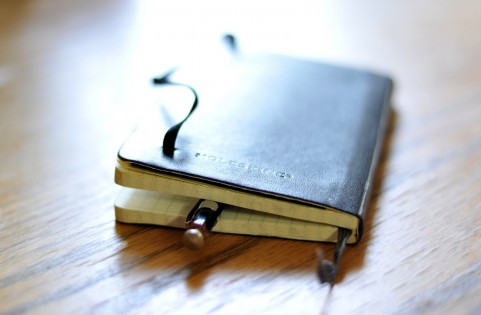
コメント